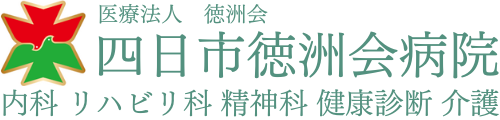院内感染対策指針 令和5年4月1日改定
詳細はこちら

四日市徳洲会病院(以下当院)は医療法人徳洲会の理念
- 生命を安心して預けられる病院
- 健康と生活を守る病院
に基づき、患者および全職員、訪問者に適切かつ安全で質の高い医療環境を提供するため、感染制御の対策に取り組むための基本的な方針を以下のとおり定める。
①趣旨
この指針は医療法人徳洲会 四日市徳洲会病院(以下当院)における院内感染防止対策および院内感染発生時の対応等における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を目的とし、下記事項について定めたものである。
1.院内感染防止対策に関する基本的な考え方
2.院内感染防止対策に関する感染管理組織構築
3.院内感染防止対策のための職員研修に関する基本的な事項
4.感染症の発生状況報告に関する基本方針
5.アウトブレイク発生時の対応に関する基本方針
6.その他院内感染に関する事項
②院内感染防止に関する基本的な考え方
院内感染を未然に防止するためその原因を速やかに特定して、これを制圧・終息させる。その為に日常より標準予防策および感染経路別予防策を実践することが重要である。全職員が院内感染防止対策を把握し、病院の理念に則った医療を提供できるように本指針をここに作成する。
③院内感染防止対策に関する管理組織
当院における院内感染発生時の迅速な対応策および院内感染の調整・対策・予防を図るため以下の組織機構を設置する。
1)院内感染防止対策委員会(以下 ICC)
病院長を委員長とし、各部署責任者および感染制御代表者を構成員として組織するICCを設ける。また、ICTで協議した感染防止に関する内容の承認・決定機関とする。ICCは病院長が任命し委員長および委員で組織化する(院長・事務長・看護部長・各部署責任者・ICTメンバー)
所掌業務
1.院内感染防止に関わる全般的な検討・推進
2.院内感染症患者発生状況に関する事項
3.院内感染サーベイランスに関する事項
4.職員に対する院内感染防止対策の教育・研修
5.院内感染防止対策マニュアルに関する事項
6.アウトブレイク発生に関する事項
7.患者等への情報提供と説明に関する基本方針
8.その他院内感染に関する事項
2)役割
院内感染防止対策委員会は、医療関連感染からすべての患者、職員を守るために日々感染防止に携わる業務を行う。また、感染症の早期発見と治療に努め、方針を明らかにし職員の教育を実践していく。病院感染に関する問題を迅速に解決できるよう窓口になる。
1.構成メンバー
院長、専任看護師、専任検査技師、専任薬剤師 4名を主たるメンバーとする。その他適格者(院長が適任と判断した者)を中心に組織する。
2.任務
①職員へ感染制御における情報の発信
②病院内、感染事例の発生やアウトブレイク発生に関すること
③病院内、感染防止対策に関すること
④抗菌薬適正使用に関すること
⑤感染対策に関する職員教育に関すること
⑥感染症発生動向調査などのサーベイランスに関すること
⑦感染対策に関する医療上、看護上の相談に関すること
⑧病院感染対策マニュアルに関すること
⑨職員職業感染防止に関すること
3.権限
①感染対策の目的のため、患者カルテを閲覧することができる
②アウトブレイク発生時の調査と介入を当該部署へおこなう
③職種、職位を問わず全職員へ感染対策の改善・指導ができる
3)感染対策チーム(以下 ICT)
ICTは、病院感染対策を充実させるための体制の強化を図り、その実践的な活動を組織横断的に行うための機関である。病院感染に関する問題を迅速に解決できるよう現場をサポートする。
1.構成メンバー
院長、専任看護師、専任薬剤師、専任検査技師4名を主たるメンバーとする。
2.任務
①1回/月程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導をおこなう
②1回/月、抗MRSA薬、カルバペネム系薬などの指定広域抗菌薬使用者の適正使用のためのミーティングをおこない、適正使用の推進を図る
③微生物学的検査に係る状況等を記した感染情報レポートを1回/週程度作成、病院感染関連検出菌の監視と介入をおこなう
④アウトブレイク、種々の感染症発生に対し、可及的すみやかな対応策を講じる
⑤職員への教育
⑥サーベイランスを積極的におこない、結果を現場にフィードバックし感染率の低減を図る
⑦感染対策マニュアルの作成・見直し、改訂を適時おこない、職員の遵守状況を確認する
⑧職業感染予防対策を実践する
⑨感染リンクナースの活動支援・指導する
⑩徳洲会グループ病院・感染管理部会・関西大阪ブロックかつ感染防止対策加算連携医療機関(1-3連携吹田徳洲会病院)との連携し情報交換をおこなうとともに、報告・助言を受ける
3.権限
①感染対策の目的のため、患者カルテを閲覧することができる
②アウトブレイク発生時の調査と介入を当該部署へおこなう
③職種、職位を問わず全職員へ感染対策の改善・指導ができる
所掌業務
・院内全体の感染予防の啓蒙活動に関する事
・院内感染防止対策マニュアルの作成と設備
・院内感染に対する対応に関する事
・アウトブレイク発生に関する事項
・院内感染の情報収集および広報に関する事
・院内感染防止の教育に関する事
・実践チームの運営に関する事
・その他院内感染に関する事項
4)感染対策リンクナース
リンクナースはICTと連携し各部署における感染防止活動推進するものである。各部署モデルとなり、感染対策を実践するための知識の充足とリーダーシップを発揮する。各部署の所属長は、リンクナースを推薦し、病院長の任命のもと活動を実践する。
1.構成メンバー
各部署の看護師(看護師歴2年目以上)
2.任務
① 定期的にICTラウンドに参加し、各部署の感染対策の実施状況を確認する
② 各部署で発生する問題点の抽出と解決策を導き出し、改善を図る
③ ICT から受けた内容を現場の職員へ伝達する
④ 感染対策マニュアルに基づき、各部署での感染対策の推進を図る
5)院内感染防止対策のための職員研修に関する基本的な事項
患者および医療従事者の感染リスクを最小限にする為、院内感染管理の基本的な考え方および具体的方策について、全職員に教育・研修を実施することとする。
1.就職時の初期研修と院内全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回以上全職員を対象に開催する。また、必要に応じて各部署、職種毎の研修についても随時開催する。
2.全職員はかならず年2回以上研修を受講しなければならない。
3.その他委託職員に対しても、必要に応じて院内感染対策に関する研修会を行う。
6)感染症の発生状況報告に関する基本方針
入院後48時間以上経過し、かつ原疾患とは別に感染した感染症をさし、医療従事者が感染し発病した場合も院内感染とする。院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるように各種サーベイランスを実施する。
1.細菌検査結果や感染報告書などから微生物の検出状況を委員会へ報告し、必要に応じて対策の周知や指導を行う。
2.院内感染対策上、問題となる各種感染症のサーベイランス
3.カテーテル関連感染、血流感染、呼吸器感染、カテーテル由来関連尿路感染などの対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施する。
7)アウトブレイク発生時の対応に関する基本方針
アウトブレイクが疑われる場合にはICTが情報収集を行い迅速に対応する。また、必要に応じて臨時院内感染防止対策委員会を招集し、感染経路の遮断および拡大防止に努める。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
8)患者等への情報提供と説明に関する基本方針
本指針は、各部署に配布・保管され、全職員が閲覧できるものとする。また、職員は患者との情報共有に努め、患者およびその家族から本指針の閲覧を要求された場合は、これに応じる。本指針の照会には各所属長が対応する。
9)感染伝播リスクのある患者とその家族への説明・同意
感染伝播リスクのある患者へ、担当医や担当看護師が、検出された微生物の事実および蔓延防止に必要な感染対策を説明し同意を得る。また、必要であれば家族にも説明し同意を得る。
10)その他院内感染に関する事項
1.最新のエビデンスに基づいたガイドラインを参考に、随時当院の院内感染マニュアルを見直し、当院の実情に合わせたマニュアルを作成する。
2.職員に院内感染対策を周知・徹底するために、院内感染対策マニュアルを各部署に配置する。
3.職員は自らが院内感染源とならないよう、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。